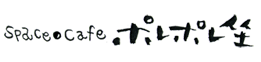Experimental film culture vol.3 in Japan ~ポレポレオルタナティブ
昨年3月に東中野ポレポレ坐で大反響・大盛況となった実験的映画/映像作品上映会を2021年も開催します!
ベルリン国際映画祭、ロカルノ国際映画祭、山形国際ドキュメンタリー映画祭など各地の映画祭で上映された作品を起点に、劇映画/ドキュメンタリー/実験映画/現代美術、ジャンルの境界を超え、映像としての強度を持つ作品が選び出された。日本国内においては未だ知られざる作家たちの新作を数多く含む、世界のエクスペリメンタルフィルムによる現在進行形の映像体験。
主催:鈴木光、石川翔平(ポレポレ東中野)
協力:ゲーテ・インスティトゥート東京、文化庁、西澤諭志、山形国際ドキュメンタリー映画祭、恵比寿映像祭/東京都写真美術館

■プログラム
新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、時間や開催の変更の可能性があります。
その際は、webなどで告知、およびご予約をいただいた方にはこちらからお知らせしますが、
何卒ご承知おきのうえ、ご了承ください。
緊急事態宣言による時短営業対応のため、
最終日19:30~のA-1プログラムのみ上映を取りやめさせていただきます。何卒ご了承ください。
▽4/29(木・祝)
12:20~【A-1 エッセイフィルム】
『Szenario』フィリップ・ヴィトマン&カールステン・クラウゼ(89分) ※ベルリン映画祭上映作
14:10~【B ビデオレタープロジェクト】 ※マル・デル・プラタ国際映画祭
UTDT-HFBK (80分)
15:50~【C 二人の父】
『God and Father and Me』鈴木光(36分)
『father』金川晋吾(60分)
+トーク20分程度(鈴木光×金川晋吾)
18:20~【D アルゼンチンの二人の作家】
『Noelia』マリア・アルシェ(15分)
『The Future Perfect』ネレ・ヴォールアッツ(65分) ※ロカルノ映画祭ベストファーストフィーチャーフィルム賞
20:00~【E 奥間勝也】
『ラダック それぞれの物語』奥間勝也(40分) ※山形国際ドキュメンタリー映画祭上映作
『ギフト』奥間勝也(40分) ※山形国際ドキュメンタリー映画祭上映作
「骨を掘る男(パイロット版)」奥間勝也(22分)
+トーク15分程度(奥間勝也 聞き手:鈴木光)
▽4/30(金)
18:00~【A-1 エッセイフィルム】
『Szenario』フィリップ・ヴィトマン&カールステン・クラウゼ(89分) ※ベルリン映画祭上映作
+オンライントーク25分程度(フィリップ・ヴィトマン 聞き手:鈴木光)
20:10~【A-2 エッセイフィルム】
『ニンホアの家』フィリップ・ヴィトマン(108分) ※山形国際ドキュメンタリー映画祭上映作
▽5/1(土)
11:30~【F「~映像と斜陽」再編 国内の美術作家による実験的な上映会の試み 】
『イローナとベラ』岡本大河(29分)
『2-8-1』小林耕平(16分)
『Dig a Hole in a Hole (Homogenize)』高嶋晋一+中川周(21分30秒)
『Echo, Post-echo』鐘ヶ江歓一(44分)
+ミニトーク15分程度(鐘ヶ江歓一×岡本大河)
14:00~【G ジェームス・ベニング+吉田孝行】※満席となりました
『On Paradise Road』ジェームス・ベニング(75分) ※2020年新作ジャパン・プレミア
『アルテの夏』吉田孝行(16分)
+トーク15分程度(吉田孝行)
16:00~【H 加藤貴文】
『15s』(60分予定)
+トーク20分程度(加藤貴文×西澤諭志)
17:40~【I 池添俊+シルヴィア・シェーデルバウアー】※満席となりました
『Memories』シルヴィア・シェーデルバウアー(15分)
『Remote Intimacy』シルヴィア・シェーデルバウアー(19分)
『池添俊作品特集』(30分程度)
+トーク30分程度(池添俊)
19:30~【A-1 エッセイフィルム】 この回は上映取りやめとなりました。
『Szenario』フィリップ・ヴィトマン&カールステン・クラウゼ(89分) ※ベルリン映画祭上映作
—————————————————————-
■料金
一回券:1500円
三回券:3600円
パス:7000円(8枚限定販売)←フリーパスは予定枚数が終了しました[4/14]
※ドリンクチケット購入不要
※席数25席限定
※予約優先 ★フリーパス・三回券の方も、なるべく事前にどの回を見るかをメールで予約してください
※予約→希望の日時とプログラム名、お名前、人数、電話番号を明記の上、experimentalfilmculture@gmail.comまでメールをしてください。チケットの精算は当日になります。フリーパスや三回券を購入希望の方はその旨もメールに明記してください。
【コロナウィルス感染対策と来場時のお願い】
※ご来場の際は必ずマスクをご着用下さいますよう、お願いいたします。
※入口での手指の消毒にご協力ください。
※席間、ステージと客席の間をいつもより開け、こまめな換気を行います。
—————————————————————-
上映スペース・ポレポレ坐にて、映像作家の鈴木光がキュレーションを務める上映イベントを開催します。自身が制作活動を続ける中で生まれてきた二項対立「物語映画と非物語映画」「ドキュメンタリーとフィクション」「インスタレーションと上映」「コンテンポラリーアートと映画」「実験映画とドキュメンタリー」これらはどのように対立しているのか、そもそも対立しているのではなく共存できるのか、その間を見つめることのできる作品が集まりました。
このイベントでは、ベルリン・ブエノスアイレス・東京を拠点に活動する映像作家/アーティストの作品、主にベルリン映画祭や、ロカルノ映画祭で上映された実験的な映像表現を見ることができます。
vol.3では、『Szenario』(フィリップ・ヴィトマン&カールステン・クラウゼの共同作品/2014年ベルリン映画祭上映作)という映画からプログラムが組み立てられていきました。この映画は、エッセイ映画というジャンルに属する作品で、1970年の西ドイツを舞台にしたある男女の日々の情事を描いています。このミニ映像祭のテーマは、制作の方法として様々な実験的な要素を含み込む潜在能力を有する「エッセイ映画」と「日常」です。
超インディペンデントで、他では見ることができない、映像作品をこの機会に是非ご高覧ください!エクスペリメンタルフィルムとは何か?ドキュメンタリーとフィクションの間とは何か!?という問いへの美術/アート/作家主義映画の一つの回答でもあるかもしれません!
(鈴木光 2004年から映像作品の制作を開始。2012—2018ベルリンに滞在。ベルリンとポツダムの大学で映画とアートを学ぶ。2018年ドイツ文化センターと共同でベルリン映画祭レポート。同年に日本へ帰国し、現在は某映像プロダクション勤務)
—————————————————————-
■鈴木光 コメント
実験映画という活動は日本にはもうほぼ存在しないし、非常に弱々しい活動になっていると思います。私は「実験映画」という古い定義で、この言葉を使うのではなく、それよりも、現在、アーティストによる映像を用いた実験的な表現や他の(オルタナティブな)試み(現代アートを含む)としての「実験的映画」という意味で、この言葉を使用したいと思っています。
ドイツで、私は映像実験のあるシーンを見てきました。日本でも多くのアーティストが映像を作っていますが、イメージフォーラムのようなところを除いては、他どこでそれを見ていいのか、場所を発見することはできません。アーティストやそのような映画制作者にとっては、日本では発表する場所の数があまりにも少ないのが現状です。
今回のこのミニ映像祭のオルタナティブなフェスティバルの意図としては、映画祭では上映されても劇場公開はされない映画を再度上映すること、美術館などのシステムの既存の枠に入らない映像作品の発表の場を作ること、アーティスト・映像制作者の発表のための場所をもっと増やしていきたいと思っていることが挙げられます。アーティストの発表の場がないと、シーンが小さくなってしまうし、いつの日か消えてしまうかもしれません。
また、今回ドイツや、その他にもアルゼンチンの作品が上映されるということは、日本での国際的な文化交流において、非常に意味のあることであると存じます。海外の映画や実験的な作品に興味を持っている日本人は多いと想像しているためです。
—————————————————————-
■テーマ
エクスペリメンタルな日常。今回上映する映画は、アーティスト・映画作家の日常の中から生まれてきます。日本では「エッセイ映画」という言葉はあまり使用されていないように存じますが、ドイツで映画を勉強する上でよく触れるジャンルです。そのため、もう一つのキーワードは「方法としてのエッセイ映画」です。ドイツで言うエッセイ映画は、流れる映像に載せて話続ける人がいます。その話し手が、どんな設定でどんなトーンで話すのか、もちろん様々ですが、一歩その使い方を間違えると、そのナラティブな映画の形がズタズタに破壊されてしまう危険性をはらんでいます。その意味でこの方法は、すごく繊細で実験的な手法であると言えます。逆に言えば、少しリズムやトーンを変えるだけで全く別な質を持った映像へ変化し、言葉と映像の組み合わせが織りなすクリエイティビティーは無限大であることも教えてくれます。そういった実験的で無限大の方法をテーマとして設定することは、他作品を見るとき、何かしらの答えや別な見方を呼び起こすことができるのではないかと考え、今回、最初に上映しようと思いついた作品がフィリップ・ヴィトマンのエッセイ形式を持った映画『Szenario』でした。ここから、他の作品のプログラムを組み立てていきました。
対象と取材者として対峙するのか、「私」として対峙するのか。なぜ映像なのか、なぜフィルムなのか。フィクショナルな視点は必要か、観察するのか。
東中野の小さな会場で世界のエクスペリメンタルフィルムを見つめてみませんか。
—————————————————————-
■各プログラム詳細
▼プログラムA
フィリップ・ヴィトマン(Philip Widmann):
フィリップ・ヴィトマンは、映画、テキスト、映画プログラムを制作しています。彼の作品は、ベルリン国際映画祭、IFFロッテルダム、Views from the Avantgarde、山形国際ドキュメンタリー映画祭、FIDマルセイユ、CPH:DOX、Visions du Réel、Wexner Center for the Arts、KWベルリン、Tabakalera San Sebastiánなどの映画祭やアートスペースで上映されています。また、Arkipel Jakarta、Image Forum Tokyo、Kassel Dokfestなどの映画プログラムを担当し、現在はEuropean Media Art Festival Osnabrückの共同プログラムを担当しています。
『Szenario』
1970年、西ドイツの代表的な都市で、表面的には整った生活を送っていた黒のブリーフケースの中身。このブリーフケースに入っているのは、中小企業の経営者ハンスとその秘書モニカの不倫関係を綿密に記録した書類。二人の性行為の詳細な記録は、同じ状況下で別の人生を歩む無限の可能性と有限の確率の場に痕跡を残している。

『ニンホアの家』
ニンホアのある家の日常を追うと、そこに住む人たちの大家族の星座が見えてくる。20世紀の歴史の流れの中で、この星座はベトナム、ドイツ、そして精神世界を繋いでいる。

——————————–
▼プログラムB
UTDT-HFBK :
このプログラムは、ブエノスアイレス のトルクァト・ディ・テラ大学(UTDT)映画コースのディレクターであるアンドレス・ディ・テッラとハンブルク美術大学(HFBK)のドキュメンタリーコース講師のネレ・ヴォールアッツが「コロナ禍の作品制作」をテーマに、共同で行なった国際ビデオレタープロジェクトです。このワークショップに参加したフィルムメーカーであり、ビジュアルアーティスト達は、別な国に住む作家へ向けてビデオを作り、それをみんなで共有しました。その後、一本の映像にまとめられ、第35回マルデルプラタ国際映画祭で上映されました。この実験的な試みを是非ご覧下さい。
参加作家は、デイヴィッド・ナサレノ・バスティト(David Nazareno Bastit)、アニカ・グーチェ(Annika Gutsche)、ニコラス・トゥリャンスキ(Nicolás Turjanski)、クノ・ゼルトマン(Kuno Seltmann)、マーロン・ウェバー(Marlon Weber)、エドュアルド・エッカー(Eduardo Ecker)、イグナシオ・オユエラ(Ignacio Oyuela)、カタリーナ・ゴンザレス(Catalina Gonzalez )、ヨハンナ・ショーン(Johanna Schorn)、アメリー・フォン・マーシャルク(Amelie von Marschalck)の10名。

——————————–
▼プログラムC
鈴木光:
1984年福島県生まれ。武蔵野美術大学彫刻学科卒業。ベルリン芸術大学大学院映像学科卒業。第一回座・高円寺ドキュメンタリーフィルムフェスティバル・第7回恵比寿映像祭・イメージフォーラムフェスティバル2017・コラボレーション作品で山形国際ドキュメンタリー映画祭(2011, 2017)に参加。アートセンターオンゴーイングやKAYOKOYUKIなどのアートギャラリーで個展も行っている。
『God and Father and Me』
家に帰ってくることが少なくなった父。小学生の時に突然、神になると言い始め、そのうちどこかに居を定めたらしかった。家に帰る回数もどんどん少なくなり、時々会うと、おかしなことを言うようになった。大学を卒業した年に、父親が住んでいるらしい場所を訪れることを決心した。初めてカメラを持って人を撮ろうと決めた作品。
*
金川晋吾:
1981年京都府生まれ。写真家。神戸大学卒業。東京藝術大学大学院博士後期課程修了。三木淳賞、さがみはら写真新人奨励賞受賞。2016年青幻舎より「father」刊行。近年の主な展覧会、2019年「同じ別の生き物」アンスティチュ・フランセ、2018年「長い間」横浜市民ギャラリーあざみ野、など。2019年より自分が書いた日記を声に出して読む「日記を読む会」を不定期で開催している。
『father 2009.11-12』
2009年9月、父は行方をくらませた。2週間ほどで戻ってきたが、仕事にはいかなくなり、ずっと家にいるようになった。父は1人で暮していた。借金も家のローンも残っていた。このままでは住む場所をうしない、生活できなくなるのはあきらかだったが、11月になっても父はかわらず仕事もせずに家にいた。私は父の写真を撮るために、父とかかわってみることにした。

——————————–
▼プログラムD
マリア・アルシェ:
アルゼンチンのブエノスアイレスにある国立映画学校ENERCの映画監督コースで学び、2010年に卒業しました。その後、ルクレシア・マルテル監督の『The Holy Girl』(2004)で主演を務めました。2018年には、自身初の長編映画『A Family Submerged』を製作し、ロカルノ映画祭で上映されました。
『Noelia』
ノエリアは、母を探している。誰彼かまわず、母と関連づけ、ブエノスアイレス中を歩き回る。カメラの前で演じる彼女の行為を、観客は濃密な映像体験として受け取る短編作品(2012)。
*
ネレ・ヴォールアッツ:
1982年、ドイツ・ハノーファー生まれ。カールスルーエ美術大学で空間演出を、ブエノスアイレスのトルクァト・ディ・テラ大学で映画を学ぶ。2016年、ベルリナーレ・タレンツ・ドックステーションに選出される。演劇作品のビデオや短編映画をいくつか監督している。ブエノスアイレスのゲーテ・インスティトゥートでは、ドキュメンタリー映画を教え、ドイツ映画のプログラムを企画しています。2013年、初の長編映画「Ricardo Bär」がBAFICIでプレミア上映され、FIDMarseille、Antofadocs、Duisburger Filmwocheで賞を受賞した。
『The Future Perfect』
この作品は、外国人が新しい社会に適応していく過程を描いた映画であり、移民としての彼女の状態が、彼女の演技スタイル、ドラマの構成、映画の装置を決定しているのです。脚本は主演のシャオビンと一緒に書き、彼女が自分自身を試し、再構築するプロセスの中で書かれました。そのため、この映画には、彼女がその時想像していたような未来も含まれており、常に変化がもたらされていきます。

——————————–
▼プログラムE
奥間勝也:
沖縄生まれ。琉球大学で文学を学んだのち上京。2011年、沖縄を舞台に制作した中編映画『ギフト』がニヨン国際映画祭(Visions du Reel:スイス)など国内外で上映。インド・ヒマラヤ山脈の麓の村に2週間滞在して制作した『ラダック それぞれの物語』が山形国際ドキュメンタリー映画祭2015年で奨励賞。
『骨を掘る男』(パイロット版)
具志堅隆松はガマフヤー(洞窟を掘る人)と名乗り、40年近く沖縄戦の遺骨を掘り続けている。監督・奥間の大叔母・正子も沖縄戦の戦没者でその遺骨は未だに見つかっていない。
監督は「会ったことのない者の死を悼むことはできるのか?」という問いを抱えながら、遺骨収集を行う具志堅の姿をカメラに収め、彼と共に大叔母の遺骨を探す。
『ラダック それぞれの物語』(2015)
村の少年ジグメットとスタンジンの夏休みの宿題は、その地に伝わる「ケサル物語」について調べること。川遊びをしたり都会に出かけたりして、大人たちに物語に聞いてまわる二人は、その話から人生の大切なことに触れていく。北インドの「今」を撮影するためフィクションとインタビューで構成した。
『ギフト』(2011)
道路拡張工事で変わりゆく那覇を舞台に、公園に住む初老の男と祖父を亡くした少年の交流を描いた作品。実際に「公園に住む男」と「その近所に住む少年」を記録したドキュメンタリーパートと、両者が役者として演じたドラマパートが混在した作品。

——————————–
▼プログラムF
岡本大河:
1994年東京都生まれ。2018年武蔵野美術大学造形学部油絵学科油絵専攻卒業。映像、インスタレーションなどを中心に制作。個展に「穴が咲いた!穴が咲いた!」(新宿眼科画廊、2015 )グループ展に「引込線/放射線」(第19北斗ビル、2019)、上映会に「~映像と斜陽」(scool、2020)など。
『イローナとベラ』
これはある家の様子を記録した映像である。女性がある過去の出来事についてこちらに話している。登場人物は二匹、あるいは三匹いる。映像が記録メディアとして機能するとき、リニアでシームレスな時間によって記録できる事実は稀であろう。むしろ、様々な時間が組み合わさる形で記録される事実の方がより自然、かつなめらかに映ることがある。
*
小林耕平:
「ヴィデオを待ちながら 映像 ─ 60 年代から今日へ」(2009、東京国立近代美術館、東京)、「小林耕平 × 高橋耕平 切断してみる。ー二人の耕平」(2017豊田市美術館、愛知)、《東・海・道・中・膝・栗・毛》MOMATコレクション(2019、東京国立近代美術館、東京)
『2-8-1』
作品コメントなし

*
高嶋晋一+中川周|Shinichi TAKASHIMA+Shu NAKAGAWA:
2014年から共同で映像制作を開始し、それ自体は画面内に見えるものではないカメラの運動性を基軸とした作品を発表。個展に「視点と支点」(MEDIA SHOP gallery、2019)、グループ展に「IMG」(Sprout Curation、2019)、「第10回恵比寿映像祭」(東京都写真美術館、2018)など。
『Dig a Hole in a Hole (Homogenize)』
眼球だけがなぜか運動を続けている屍体のように、計器が壊れた状態にもかかわらず「調整」という振る舞いだけが残っているカメラが映し出す映像を想像してみよう。そのとき像として結ばれているのは何か。カメラなどの計器には視覚的な像に還元できない調整それ自体の属する現実がある。調整と穴(死界=デッドゾーン)をテーマとした映像作品。
*
鐘ヶ江歓一:
美術作家。1992年生まれ、2017年に武蔵野美術大学造形学部油絵学科油画専攻卒業。2018年にNPO 法人AIT/エイト、文化庁主催のアーティストプラクティス2017修了。映像、インスタレーションを中心に人がものを捉える際の知覚の形を模索。上映会企画やダンサー、パフォーマンスアーティストと映像を通して協働もする。
『Echo, Post-echo』
出来事の手前にある、場作りに注目してみる。場作りが決定的な出来事を呼び込めず、空回りした前フリを続ける。
この連続性を映像の時間で呼ぶならば、展開とも言える。それは、前後を伴う流れでしかなく、ある側面では内容を置き去りに時間を進めてしまう。意味が定着していく、その手前で空振りを続ける運動を記述する試みの物語。
——————————–
▼プログラムG
ジェームス・ベニング(James Benning):
1942年生まれ。米国の映画作家。カリフォルニア芸術大学教授。1970年代からこれまで長編短編あわせて50本以上の作品を制作している。『RR』(07)、『ルール』(09)、『スモール・ロード』(11)、『ステンプル・パス』(12)など、多くの作品が日本でもイメージフォーラム・フェスティバルや恵比寿映像祭などで上映されている。
『On Paradise Road』(2020年 75分)
長時間の固定ショットで風景を撮影する風景映画の作家として知られるベニングだが、本作はコロナ禍でロックダウン中のカリフォルニアの自宅の内部だけで撮影された作品である。しかし、その主題と撮影スタイルは本作でも継承されており、無人のキッチンや壁に飾られた絵画などを過剰な長回しで映し出し、作家本人の日常の風景が再現されている。

*
吉田孝行(Takayuki Yoshida):
1972年生まれ。映画美学校で映画制作を学ぶ。これまで30か国以上の映画祭や展覧会で作品を発表している。近作に『ぽんぽこマウンテン』(16)、『タッチストーン』(17)、『モエレの春』(19)、『エイジ・オブ・ブライト』(21)など。共著に『アメリカン・アヴァンガルド・ムーヴィ』(森話社)など。
『アルテの夏』(2019年 16分)
かつて炭鉱で栄えた町の山の中にある閉校となった小学校の木造校舎。その一部は現在も地元の幼稚園として利用されている。この町で生まれ育った彫刻家を中心に閉校となった学校施設を芸術広場として再生する取り組みが行なわれている。自然と人と彫刻が融合した安らぎの空間。広場にある水路や池で水遊びをして過ごす子ども達のある夏の一日。
——————————–
▼プログラムH
加藤貴文:
1983年埼玉県生まれ、東京都在住。武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻油絵コース修了。イラストレーター・映像作家。撮影・映像制作業務のほか、ニュースアプリ「SmartNews」のマスコットキャラ「地球くん」の日替わりイラストを担当。主なグループ展に「むびぐみX」(金沢アートグミ)など。
『15s』
作品について「15s」は自分のウェブサイトのトップページに設置しているビデオスライドショーです。日々撮りためるホームビデオをクリップ単位でアップロードし続け、それをシャッフル再生することで自己紹介映像としています。近年はこれらを1時間毎に投稿するTwitterアカウントや、1日単位のまとめを投稿するYouTubeチャンネルも運営し、「まとめない」映像の流し続け方を探求しています。

——————————–
▼プログラムI
シルヴィア・シェーデルバウアー(Sylvia Schedelbauer):
1993年、東京に生まれたシルヴィア・シェーデルバウアーはベルリンに移住し、現在に至る。ベルリン芸術大学で(Katharina Sieverdingの元で)学びました。彼女の映画は、主に拾った映像やアーカイブ映像を詩的に操作することで、広い歴史的物語と個人的な心理的領域の間を行き来します。主な上映作品 ベルリン国際映画祭、トロント国際映画祭、オーバーハウゼン国際短編映画祭、ロンドン映画祭、ニューヨーク映画祭、ロバート・フラハティ国際映画セミナー、スタン・ブラッケージ・シンポジウムなどで上映されています。受賞歴:VG Bildkunst賞、ドイツ映画批評家賞、ガス・ヴァン・サント賞(最優秀実験映画賞)など。シェーデルバウアーは、ハーバード大学ラドクリフ高等研究所の2019/2020年度フェローでした。
『Memories』
バブル期の日本で育った一人の女性。なぜ彼女の両親は昔のことを話さなかったのか?彼女の家族のアーカイブから見つかった箱いっぱいの写真を使って、フィルムメーカーは家族の歴史の1つのバージョンを構築しようとします。
『Remote Intimacy』
ホームムービー、教育用フィルム、ニュース映画などの様々な種類のドキュメンタリー映像と、様々な個人の記憶と文学的なテキストを組み合わせた、一見個人的な物語を組み合わせたファウンド・フッテージ・モンタージュである。繰り返し見る夢の記述から始まるこの映画は、「記憶」を詩的に増幅したものであり、その連想的な物語構造によって、文化的な離散の問題について考える場を開くことを願っています。
*
池添俊:
1988年香川県生まれ。個⼈の声(記憶)を集めて、普遍的な声(意識)として再構成する。中国人の継母との生活を描いた『愛讃讃』(2018)が国内外の映画祭で上映。育ての親である祖母の声から作った『朝の夢』(2020)が第32回マルセイユ国際映画祭から正式招待される。
『愛讃讃』
人は分かり合えないもの。そう感じる原点には中国人の元義母の存在があった。四川語と関西弁が飛び交い、母の一人称を「お姉ちゃん」と呼んでいた過去を期限切れの8mmカラーリバーサルフィルムで映し出す。そのフィルムの使用期限はお姉ちゃんが出て行った年だった。
『his/her』
2019年逃亡犯条例に反対する民主化デモが起こる前夜の香港にて撮影。 大勢の人々が行き交う都会では、どこにいても人は他人の気配を感じながら生きている。不安、焦燥、寂しさ、慕情。街の中で一人、どこか遠くで消えてなくなりたい、と思った時にはもう、住処へ帰る道順を考えている。口笛を吹いていたのは、誰?
『揺蕩』
2019年逃亡犯条例に反対する民主化デモが起こる前夜の香港にて撮影。 香港を旅した時に見た風景は、昔夢で見たような懐かしさがあった。小さな島にひしめき合う高層ビルの下に広がる商店街や市場。未来的でありながら時間が退行するような佇まいの街。日本に帰国しニュース動画を見ると、その街に火炎瓶が飛んでいた。風向きに合わせて世界や人はすぐ変わる。自分が見ていたものは夢だったのか?普段の生活と一枚壁を隔てた先にある微かなゆらぎを拾い集めた。
『あの人の顔を思い出せない』
見ようとすればするほど見えなくなる。人は自分が気になる部分にしか目を向けず、受け取った情報で意識を構築する。本当のことを知ろうとした(知った)時には事態は後戻りできなくなっていることがある。画面上をわざと欠落させることで、鑑賞者の意識がどこに落ち着くのかを実験した。
『朝の夢』
目覚めた時にはあの人はもういないかもしれない-
私にとって「母」とは、私を育ててくれた「祖母」だった。無常の愛を与えてくれた母が初めて語った、最愛の人との出会いと別れ。