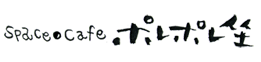映画一揆外伝 ~破れかぶれ~『LEFT ALONE』一挙上映
■日時:2018年6月30日(土)
■受付・開場:18:00
■開映:18:30 「LEFT ALONE1」93分
20:05 休憩
20:15 「LEFT ALONE2」109分
■料金:1,500円(当日券のみ)
■お問い合わせ:090-4395-4852(担当:高橋)
Email: spiritualmovies@hotmail.co.jp
二〇一八年一月二一日、西部邁さんが亡くなった。
その日、私は『LEFT ALONE』を撮るために集めた参考資料の整理をしていた。
偶然だった。この映画のために集めた資料は膨大で、
吉岡文平と桑原広考、私の三人で分担して保管してきたのだが、
桑原から「引っ越しを機に整理をしたい」との申し出があったため、
映画一揆の若いメンバーらと桑原邸に集まり、仕分けをすることになったのだ。
「読みたい!」という初々しい声や情熱とともに、
おおよそ段ボール五箱分の本はどんどん若者たちの手に渡っていった。
それは次世代に”何か”が受け継がれていく様子が具体的に目に見える場だったので、
清々しく気分がよかった。それでも四、五冊は私の手元に残すことにした。
付箋だらけで、書き込みがしてあったり、傍線が引いてあったりと、
他人に渡すには恥ずかしい本だった。
その中の一冊に西部さんの『六〇年安保―センチメンタル・ジャーニー』もあった。
私はその表紙を撫でさすり、頁をめくって字面を眺めた。
そうしていると、取材に備えて繰り返しその本を読んでいた時間がよみがえってきた。
その日の夕方のニュースで西部さんの訃報を聞いたのである。
翌日、東京は大雪が降った。
西部さんの死後、「『LEFT ALONE』を観たい」「上映してほしい」
「上映しないのか?」という声をたくさんいただいた。
反応が遅くなってしまったが、六月に上映することが決まった。観てほしい。
(井土紀州)
__
『LEFT ALONE 1』
監督:井土紀州
出演:絓秀実 松田政男 西部邁 柄谷行人 鎌田哲哉
ナレーション:伊藤清美
製作:吉岡文平 撮影:伊藤学 高橋和博
音楽:太陽肛門スパパーン 整音:臼井勝
企画・製作:スピリチュアル・ムービーズ
2005年/93分/DVCAM/カラー
『LEFT ALONE 2』
監督:井土紀州
出演:絓秀実 松田政男 柄谷行人 津村喬 花咲政之輔
ナレーション:伊藤清美
製作:吉岡文平 撮影:伊藤学 高橋和博
音楽:太陽肛門スパパーン 整音:臼井勝
企画・製作:スピリチュアル・ムービーズ
2005年/109分/DVCAM/カラー
【解説】
1968年生まれのひとりの映画監督が、68年を探る映画を撮る。
学生たちの政治運動。革命。そして、68年を境に政治運動は
カウンター・カルチャーと結びつき、80年代にはサブカルチャーとして脱色化されていく…。
68年は、ニューレフト運動にとって決定的な転回点であった。
映画は、2001年に早稲田大学で勃発したサークルスペース移転阻止闘争において
非常勤講師でありながら学生達と共に大学当局と闘う批評家、
絓秀実の姿を捉えることから始まり、松田政男、柄谷行人、西部邁、津村喬にいたる
60年代の学生活動家たちと対話を重ねていく。
『レフト・アローン1』では、ニューレフトの誕生から、花田清輝と吉本隆明の論争、
68年の安保闘争に至る過程を絓秀実、松田政男、鎌田哲哉、柄谷行人、西部邁とともに
様々な角度から検証し、『レフト・アローン2』では、68年革命の思想と暴力という問題、
1970年7月7日の華僑青年闘争委員会に始まる在日朝鮮人・中国人等に対する
反差別闘争の衝撃、毛沢東主義の新たな可能性から、
現在の大学再編と自治空間の解体をめぐって、ニューレフトの行方が、
絓秀実、松田政男、柄谷行人、津村喬、花咲政之輔によって語られていく。
体制への反逆。60年安保という激動期。思想と暴力。それぞれの闘争と転機。
悲劇から喜劇へ。そして、今なお左側を歩き続けていくことの孤独。
早稲田の路地を歩くすがの後姿に、彼方に向かって糞を転がしつづける
スカラベサクレ(糞転がし)の姿が重ねられる…。
【監督コメント】
もうひとつの映画/井土紀州(2005年公開時のコメント)
私たちは映画を作る。
何かについて考えながら作る。
では、いったい何について考えているのか。
テーマ? 物語? それとも映画そのもの?
当然、それらすべてについて考えなければならないが、
さらにその先に私たちを考えさせてやまない何かがある。
それはあくまでも未知のものであり、いつもぼんやりとした靄につつまれている。
それはいずれ私たちが作った映画を差し出すべき観客という存在だ。
この不特定多数の漠然とした存在について思考を巡らせたとたん、
私たちの映画作りに臆病風が吹き始める。
それって面白いの? 退屈じゃない? 分かりにくくない?
彼らは時に素朴に、時には目尻を吊りあげて私たちを詰問する。
彼らの問いに頭を悩ませ、逡巡したあげく、私たちはひとつの結論に達する。
私たちが映画を作るために何かを考えるのは、
映画を見る彼らに何も考えなくさせるためでは決してないのだ。
「観客を作られた世界に引き込み、そこで興奮と陶酔のひと時を味わせるのではなく、
むしろ現実に対する思考を促し、観客の活動力を鼓舞する」
ブレヒトの演劇に対するこの態度を、私たちは私たちのもうひとつの映画のために、
もう一度検討する必要がある。